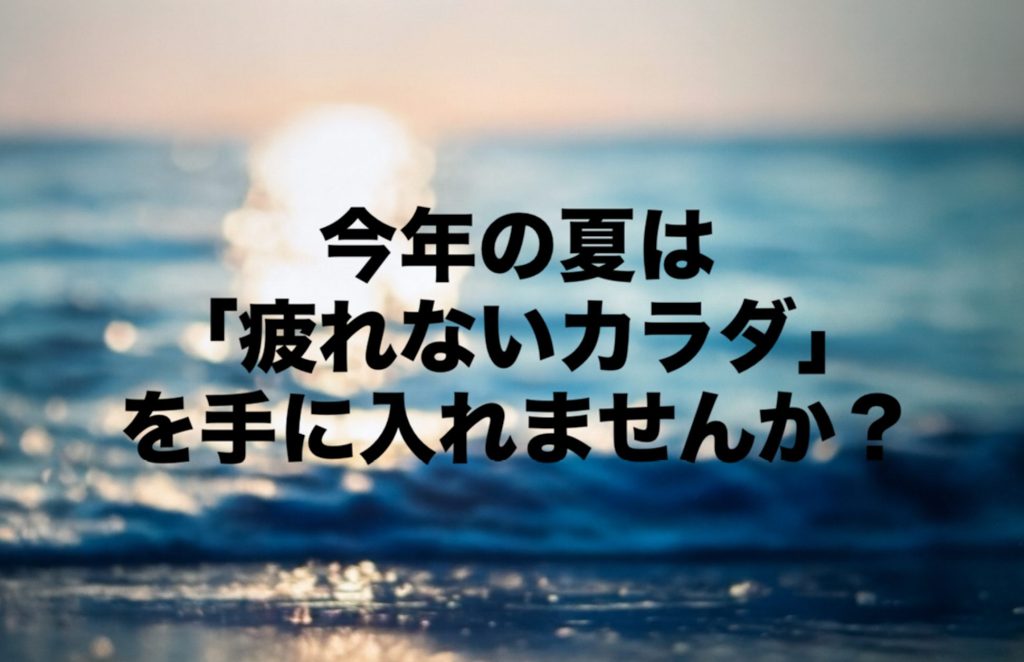今年の夏は「疲れないカラダ」を手に入れませんか?
BLOG
2025 / 08 / 17
最終更新日:2025年8月19日
今年の夏も猛暑が予想されています。
毎年「夏になると疲れやすい」「日中に眠気が抜けない」「なんだかやる気が出ない」と感じる方は多いのではないでしょうか。
このような夏特有の疲れは、単なる気のせいではなく 体の仕組みや生活習慣に原因 があります。
本記事では、「夏 疲れない」体作りの方法 を徹底解説します。食事・睡眠・運動・生活リズムを見直すことで、夏バテやだるさを予防し、快適な毎日を過ごせるようになります。
目次
暑さによる自律神経の乱れ
夏は体温調節のために自律神経がフル稼働します。
大量の汗をかいたり、冷房で急に冷えたりといった気温差が続くと、自律神経が乱れ「疲れやすい体」になります。
その結果、集中力の低下や倦怠感が出やすくなります。
睡眠の質が下がる理由
熱帯夜は深部体温が下がらず、深い睡眠に入りにくい環境です。
扇風機や冷房を使っても快眠できず、翌日に疲れを持ち越す人が多いのはこのためです。
水分・ミネラル不足の影響
夏は汗でナトリウムやカリウムなどのミネラルが失われます。
体内の水分バランスが崩れると、だるさや頭痛、筋肉のけいれんが起き、疲労感が強まります。
冷房との上手な付き合い方
オフィスや電車では冷房が効きすぎていることもあります。
長時間の冷えは血流を悪くし、肩こりや倦怠感を招きます。
持するポイントです。
疲れないカラダをつくる生活習慣

朝のスタートで1日の体調が決まる
夏は朝から暑いため、起き抜けにだるさを感じる人が多いです。
起床後すぐに 常温の水をコップ1杯飲む ことで体を目覚めさせ、自律神経の切り替えがスムーズになります。
朝日を浴びてセロトニンを活性化させることも重要です。
夏に最適な栄養バランス
炭水化物・タンパク質・ビタミン・ミネラルをバランスよく摂ることが、疲れない体作りの基本です。
特に夏は「ビタミンB群」「クエン酸」「マグネシウム」を意識して取り入れると疲労回復が早まります。
疲労回復に役立つ食材リスト
豚肉(ビタミンB1豊富でエネルギー代謝を助ける)
レモン・梅干し(クエン酸で疲労物質の乳酸を分解)
トマト・きゅうり(カリウムでむくみ解消)
納豆・豆腐(タンパク質とマグネシウムで筋肉をサポート)
快眠のための寝室環境づくり
エアコンの設定温度は 26〜28℃、扇風機を壁に向けて空気を循環させるのが理想です。
寝具は通気性の良いものを選び、寝る直前のスマホ使用を控えることで睡眠の質が上がります。
日中の小休憩の重要性
長時間の作業は自律神経を消耗させます。
1時間に1回は5分休憩 を入れることが疲労の蓄積を防ぎます。
冷たい飲み物よりも常温の水や麦茶が効果的です。
夏バテ防止に効く運動習慣

軽い有酸素運動で代謝を高める
ウォーキングや軽いジョギングは血流を良くし、自律神経を整えます。
夕方や朝の涼しい時間に行うと効果的です。
ストレッチで血流改善
オフィスや自宅で簡単にできるストレッチは、肩こりやだるさ解消に役立ちます。
特に首・肩・ふくらはぎを伸ばすことで、血液循環がスムーズになります。
筋トレで基礎体力を強化
夏に疲れない体作りには、筋肉量を維持することも重要です。
スクワットやプランクなどの自重トレーニングを取り入れると、基礎代謝が上がり、だるさを感じにくくなります。
屋内と屋外の運動バランス
真夏の炎天下での運動は危険です。
室内での筋トレやヨガを中心にしつつ、朝や夕方に軽い屋外運動を組み合わせると無理なく続けられます。
夏を快適に過ごすための食生活改善

水分補給のベストタイミング
一度に大量の水を飲むより、こまめに少しずつ 補給するのが正解です。
スポーツドリンクと経口補水液の違い
スポーツドリンク → 汗をかいた後の糖分・電解質補給に経口補水液 → 脱水症状が疑われるときに有効
普段から常用するなら、糖分控えめの麦茶やミネラルウォーターがおすすめです。
ビタミン・ミネラルで疲労回復
特に夏に不足しがちな ビタミンC・マグネシウム・カリウム を意識して摂りましょう。
果物や野菜をスムージーにして取り入れるのも効果的です。
胃腸に優しいメニューの選び方
冷たい飲み物やアイスの食べすぎは胃腸を弱めます。
うどんやそうめんに薬味を添えたり、消化の良いタンパク質(豆腐・白身魚)を組み合わせると、胃に負担をかけずに栄養を摂取できます。
日常でできるストレスケア

呼吸法で自律神経を整える
腹式呼吸をゆっくり繰り返すことで、副交感神経が優位になりリラックスできます。
寝る前に実践すると、睡眠の質も高まります。
マインドフルネスで心を軽く
5分間の瞑想や、自然音を聞きながらの深呼吸は、ストレス軽減と集中力アップに効果があります。
自然と触れるリフレッシュ方法
緑の多い公園や森林を散歩するだけで、自律神経が整い「疲れない体」へと近づきます。
週末に自然と触れる時間を作るのも、夏の疲労対策になります。
食事・運動・睡眠の実践テクニック集

食事編:疲れない体をつくる食習慣
朝食にタンパク質を取り入れる:卵やヨーグルトで代謝をスタート
昼食は炭水化物+野菜でバランスを:そうめんには野菜や肉をトッピング
夕食は消化に優しいメニュー:豆腐や魚を中心に胃腸を休める
間食にはフルーツやナッツ:ビタミンとミネラルを補給
運動編:夏バテ知らずの運動習慣
朝の軽いストレッチ:寝起きのだるさを解消
夕方ウォーキング:涼しい時間帯に代謝を高める
トレーニング:スクワットやプランクで基礎代謝維持
ヨガや深呼吸:自律神経を整え、リラックス効果も
睡眠編:質の高い休息をとるコツ
寝室の温度は26〜28℃:冷房+扇風機で空気循環
寝具は通気性のよいもの:リネンやコットン素材が最適
就寝1時間前はスマホ断ち:ブルーライトを避ける
寝る前に白湯を一口:体をリラックスさせ眠りやすく
よくある質問

Q1. 夏の疲れは「加齢」のせいですか?
A. 年齢を重ねると基礎代謝や筋肉量が減り、疲れやすさが増すのは事実です。しかし生活習慣を工夫すれば、年齢に関係なく「疲れない体作り」は可能です。


Q2. 水分補給は水だけでいいですか?
A. 普段は水や麦茶で十分です。ただし、汗を大量にかいた後は塩分を含むスポーツドリンクや経口補水液が効果的です。


Q3. 夏は運動を控えたほうがいいですか?
A. 過度な炎天下での運動は危険ですが、運動そのものを控えるのは逆効果です。軽いウォーキングや室内運動で代謝を維持することが「疲れない体」につながります。


Q4. 冷房を使うと体がだるくなるのですが、どうしたらいいですか?
A. 冷えすぎると血流が悪化し、だるさを感じやすくなります。設定温度を高めにし、羽織り物を用意するなど「冷えすぎ防止」を心がけましょう。


Q5. サプリで疲労回復はできますか?
A. サプリはあくまで補助です。まずは食事から栄養を整え、必要に応じてビタミンB群やマグネシウムのサプリを取り入れると効果的です。

まとめ – この夏は“疲れないカラダ”で乗り切ろう
夏は自律神経の乱れや睡眠不足、水分・栄養の不足から「疲れやすい」状態になりやすい季節です。
しかし、食事・運動・睡眠・生活習慣を工夫すれば、夏でも疲れない体作り は可能です。
朝は水と朝日で体をリセット
ビタミン・ミネラルを意識した食生活
軽い運動とストレッチで代謝をアップ
睡眠環境を整え、深い眠りを確保
ストレスケアで心身を調える
今年の夏こそ「疲れないカラダ」を手に入れ、猛暑を快適に乗り切りましょう。
無料体験実施中!
BEYOND湘南藤沢店 公式LINE はこちら
BEYOND湘南藤沢店 Instagram はこちら
この記事の著者

岩堀 マーヴィン 哲 ジョジョ
湘南藤沢店トレーナー